あなたの家には、「持っているけど使っていないもの」はどれくらいありますか?
それは本当に必要なものでしょうか? それとも、ただ「持っているだけ」になっているでしょうか?
近年、「ミニマリズム」や「断捨離」という言葉が広まり、モノを減らすことが推奨されるようになりました。
「少ないほどいい」「スッキリした暮らしが豊か」という考え方は、確かに魅力的に聞こえます。
しかし、単にモノを減らすことが「手放すこと」の本質ではありません。
手放すこととは、「本当に必要なものを選び取ること」。
では、私たちはなぜ「手放すこと」に迷うのでしょうか?
そして、手放すことで得られるものとは何なのでしょうか?
この記事では、「手放す」という行為の本当の意味を探りながら、
「モノを減らすこと」と「本当に大切なものを見極めること」の違いについて考えていきます。
「手放す」とは、ただモノを減らすことではない
「手放すこと」の本質は、「モノを減らすこと」ではなく、「本当に必要なものを選び取ること」 。
その選び取る過程で、不要なものが自然と減るだけなのです。
手放すときに生まれる3つの感情
手放すとき、人は何を感じるのだろうか?
- 「何も感じない」こともある。
- 「寂しさ」を感じることもある。
- 「もったいない」と感じることもある。
「何も感じない」
不要なものを手放すとき、意外と何も感じないこともある。
それは、そもそも「持っていること」自体に意味がなかったからかもしれない。
「寂しさ」を感じる
長年使っていたもの、大切にしていたものを手放すとき、「もう使わないけど、捨てるのはなんだか寂しい…」と感じることがある。
しかし、それは「モノ」ではなく、そのモノにまつわる 思い出や経験 への愛着なのではないか?
「もったいない」と感じる
結局まだ使ってないし、わざわざお金かけたのに…。
それは、モノを見ているのではなく、損している感を感じたくないのでしょう。
一生そこに居座られる場所と時間とお金、そうやってあなたの思考を奪うモノにそれだけの価値があるでしょうか?
思い出は手放さなくてもいい
思い入れがあるものだから、捨てられないと感じる時もあるでしょう。
私はそんなとき、「モノを心に住まわせる」 という感覚で捉えるようにしている。
モノ自体は手放しても、思い出は記憶の中に残り続ける。
昔はよかった。みたいな感覚があるじゃないですか。
それは「回顧バイアス」と呼ばれるもので、過去の出来事を実際よりも美化して記憶する心理的な傾向があるそうだ。
そう考えると、手放すことは『思い出をより美しく残す』行為 なのかもしれない。
手放すことで気づくこと
かつて、私はモノをため込んでいた。
どこに何を置いたかすら分からないほど、モノであふれていた時期もある。
「これがなくなったら、本当に困るかもしれない。」
そう思いながら、いざ手放してみたら 何も困らなかった。
「ないと不便だと思っていたもの」が、実際には「なくても問題ないもの」だったのだ。
「モノがないこと」が怖いのではなく、「モノがないことで不自由になるかもしれない」という不安が怖かっただけ。
しかし、手放してみると、
- 日常生活に支障はなかった
- 好きなことをする時間も読書の時間も変わらなかった
- 「なくなることへの不安」そのものが消えた
この経験を通して、「ないこと」自体は問題ではなく、「ないことを怖がる気持ち」が問題なのだと気づいた。
むしろ、掃除する手間や、どこにモノがあったかを探す時間が減りました。
個人的に好きだったのは、「自分の好きなモノ美術館」ができたような感覚を感じれたことです。
手放すことによるメリット
手放すことに関しての一番のメリットは、モノを管理するコストが減ったことです。
コストは、置く場所・手入れする時間・諸々のお金・思考時間などです。
- 時間の余裕が生まれる
- 片付けや管理にかかる時間が減る。どこにモノがあるかすぐにわかる。
- 選択のストレスが減る
- 服が多すぎると「何を着るか」迷うが、選択肢を絞れば決断が速くなる。
楽しんで選んでいるのであれば、問題ありません。
- 服が多すぎると「何を着るか」迷うが、選択肢を絞れば決断が速くなる。
- 精神的な軽さを感じる
- →モノが少ないと、空間がスッキリして頭の中も整理される。
モノが少ないと没頭もしやすいですし、好きな物ばかりになるので好きな空間を眺めるだけでも幸せに感じます。
個人的に時間の余裕が生まれたのが、一番うれしいです。
どんな人でも変えられないものが1日24時間という、時間ですから。
自分だけの時間を楽しみましょう。
「持つこと」に安心を求める私たち
なぜ人は、モノを持つことに安心を求めるのか?
持つことには安心感がある。
いつでも手元にあるということが、選択肢の自由を生む。
しかし、「持つこと」の価値は、必ずしも「使うこと」に直結しない。
「持っているだけで満足してしまう」という心理は、「使うこと」への意識を鈍らせることがあるのだ。
現在、モノを 「持つこと」よりも「使うこと」 に価値を置いている「レンタル文化」が復活しつつある。
- サブスクリプションサービス(音楽・映画・本)
- シェアオフィス・シェアハウス
- カーシェア・自転車シェア
所有することよりも、必要なときに使うことが重視されるようになってきた。
これは、持ちすぎることで管理が大変になり、シンプルに生きたいと願う人が増えたからだろう。
「持つこと」よりも「使うこと」に価値を置く。
それだけで、モノとの関係は変わる。
「手放せない」と感じたときの考え方
「手放したいけど、どうしても捨てられない……。」
そう感じるときは、次の考え方を試してみてほしい。
- お店は、私のものを預かってくれている
- これ、今の私にとって本当に必要?
- 一時的に離れてみる
お店は、私のものを預かってくれている
必要なら、また迎えに行けばいい。
手放したとしても、本当に必要なものはまた手に入る。
モノの本質を見誤らないで。
場所や時間・管理費を進んで出してくれているのだから、感謝してお金を渡せます。
これ、今の私にとって本当に必要?
過去の自分が必要としていたからといって、今の自分も必要とは限らない。
「未来のために」と思って持ち続けているものほど、「今の自分」にとっては不要だったりする。
読めない本なのに、かっこいいからと言って買っておいてある本とかありませんか?
私はありましたね。
一時的に離れてみる
「とりあえず捨てるのが怖い……。」というときは、別の場所に保管してみるのも手。
一度距離を取ることで、意外と「なくてもいい」と思えることも多い。
1年後処分するためのスペースを作って、入れてください。
どうしても必要であれば、とりに行きますから。
そこまでするものってなかなかありませんが。
断捨離をするステップについて
実際に行う断捨離については、断捨離のコツを交えて説明している記事があるので参考にしてください。
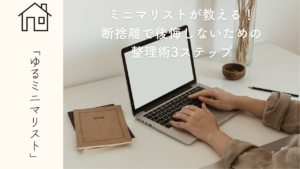
まとめ:「手放す」とは、選び取ること
「手放すこと」は、単にモノを減らす行為ではない。
それは 「本当に必要なものを認識する行為」 であり、「自分の感性を大切にすること」 でもある。
- ✅ ただ「持っているだけ」のものはないか?
- ✅ それは、本当に「使っている」と言えるのか?
- ✅ “持っているだけ”のモノが、本当に必要なモノだと言えるだろうか?
「持つこと」が安心ではない。「使えること」こそが、自由につながる。
